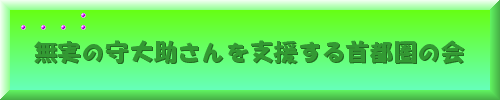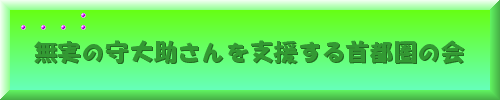|
〜科学を度外視して書いた間違いだらけの決定文〜
仙台高裁再審請求棄却決定のおかしな内容の数々
仙台高裁(裁判官:嶋原文雄、行方美和、根崎修一)は、2018年2月28日に、弁護側の即時抗告を棄却する決定を行いました。決定文書は、弁護側がこれまで繰り返し、文書や協議の場で説明してきた、鑑定の信頼性等に関する問題について、地裁の決定をほぼ踏襲し、一方的に検察の主張に寄りかかり、正確な理解も正当な根拠もなしに、これを否定したものです。即時抗告申立から4年もあったにも関わらず、弁護側が再三求める証人尋問や証拠開示にも応じず、実質的な審理は何も行わないまま、とんでもなくいい加減な結論を出したと言わざるを得ない内容です。
特に特徴的なのは、鑑定に関する科学的論点のほとんどで明らかにおかしな理解や判断を行っていることです。決定文書の内容のほとんどが検察の意見書や、科捜研の鑑定人であった土橋氏の意見書をコピーしたものですが、元々おかしなそれらの主張を、正確な理解もなしに、表現をもじって使ったり、踏み込んで勝手な解釈をしているために、さらに質が悪く低劣な、とんでもない素人文章になっています。
また、不足した知識を無理に埋め合わせて強引に結論を導くために、随所で「〜も否定できない」「・・され得ることを排斥する内容ではない」などの表現を多用して誤魔化し、弁護側に対して不当な完全証明(無実の証明)を求めています。このようなことは、再審においても『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判の原則が適用されるとした白鳥決定に明らかに反するもので、刑事裁判の原則に反するのみならず、科学を全く無視して審理を行ったという意味で、民主主義の根幹をも揺るがすものです。
以下に、仙台高裁の決定の中から、鑑定問題を中心におかしな部分を示します。
鑑定問題の争点や質量分析の基本的な解説などについては以下の資料をご覧ください。
http://daisuke-support.la.coocan.jp/kanteiron.pdf
※本文章は、弁護団の見解とは一切関係がありません。当会の文責によるものです。
仙台高裁棄却決定 P11〜12
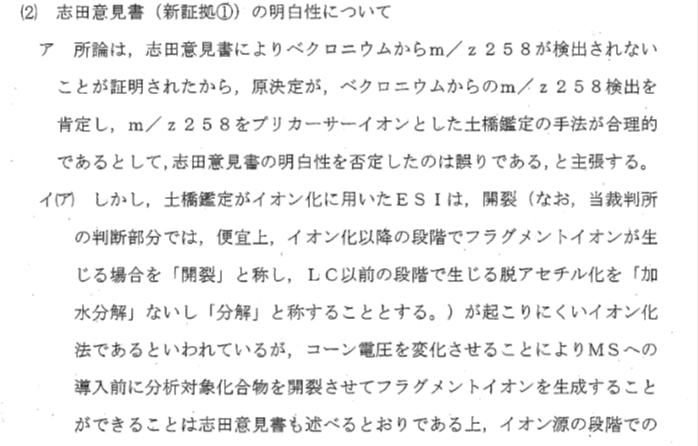
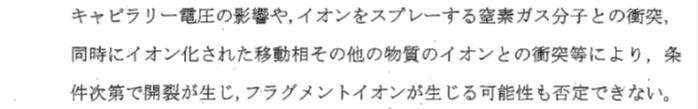
⇒ 「コーン電圧を変化させることによりMSへの導入前に分析対象化合物を開裂させてフラグメントイオンを生成することができることは志田意見書も述べるとおりである上・・」とのことですが、志田意見書に記載されている実験は、(検察の確定上告審段階での主張(=m/z258はベクロニウムから開裂によって生じた)へ反論するために、)通常のESI(エレクトロスプレーイオン化)法ではなく、意図的に(コーン電圧を高圧にする)過酷な条件を作り出して分析対象化合物の開裂を引き起こす手法で、この実験を根拠にして通常のESIでの開裂の可能性に言及することは全くの見当違いです。また、最後の文章の「イオン源の段階での・・・生じる可能性も否定できない。」は確定上告審での検察の主張をそのまま取り上げたものですが、勝手な仮説に過ぎず、全く根拠が示されていません。「可能性も否定できない」などと言えば、何でも言えてしまいます。「疑わしきは被告人の利益に」は再審制度にも適用されるべきであり、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じれば再審を開始できるとした白鳥決定に反し、原則を被告人ではなく検察側に適用しているようなものです。
仙台高裁棄却決定 P12
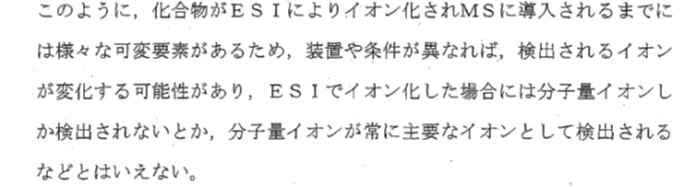
⇒ 実際にベクロニウムをESIイオン化により質量分析した国内外の論文では、すべて分子量関連イオン(分子イオン(m/z557)または分子イオンにプロトンが付加した2価イオン(m/z279))が検出されています。ベクロニウムをESIイオン化により質量分析してm/z258が(ベースピークとして)検出されると言ってるのは世界中で土橋(およびその共同研究者、以下略)だけです。「装置や条件が異なれば、検出されるイオンが変化する可能性があり」は検察の受け売りですが、「化合物がESI(エレクトロスプレーイオン化)によりイオン化されMSに導入されるまでに様々な可変要素があるため」としか説明されておらず、様々な可変要素とは具体的に何を指すのか、なぜ、どういう機序で検出されるイオンが異なるのか、全く根拠が示されていません。仮に検出されるイオンが変化するとしても、なぜ、鑑定資料が残されておらず、再鑑定もできない、いくらでも偽造可能な内容の鑑定書しか残っていない鑑定で、土橋だけが検出したとするイオンを信用しなければならないのでしょうか?それでは客観性が全くないものを証拠として認めることになってしまいます。
なお、高裁は「分子量イオン」という言葉を用いていますが、「分子量イオン」という言葉は質量分析の世界では使われていません(分子イオンまたは分子量関連イオン)。このようなところからも、裁判所が質量分析を全く理解していないことがうかがえます。この場合、正しくは「分子量関連イオン」(分析対象化合物の分子量を反映するイオン)です。
仙台高裁棄却決定 P12
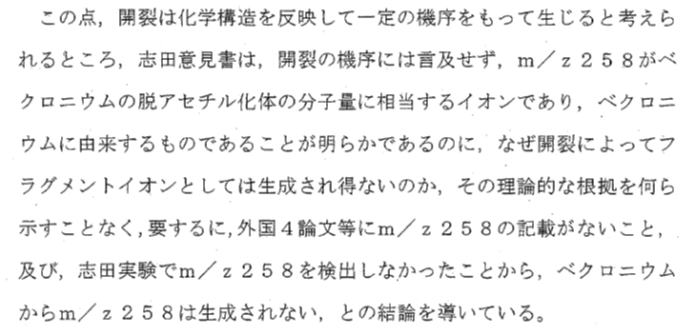
⇒ 「開裂の機序」が具体的にどういう説明を期待しているのかわかりませんが、それを言うなら、そもそも検察もm/z258がベクロニウムから開裂によって生じる機序を一切示していません。「理論的な根拠」とのことですが、ある化合物から開裂によって特定のイオンが絶対に生じ「ない」ことの理論的な根拠を示すなど、一般に不可能もしくは不可能に近いはずで、そんなことを求めるのはナンセンスです。だから実験をして確かめているわけです。なお、裁判所は、加水分解等で脱アセチル化が起こる化学変化と、原子や分子の衝突で開裂が生じる機序を一緒くたにして、加水分解で生じるくらいだから、開裂でも生じることはあり得るだろうと言いたいようですが、水の電離作用による加水分解と、物理的エネルギーをぶつけることで開裂が生じる機序は全く異なるものであり、それらにより得られるイオンが異なるだろうことは科学(化学)的なセンスからすれば当然のことです。裁判所のこのような言い分は、基本的な科学(化学)的センスを持ち合わせていないところから生じていると考えられる、素人解釈に過ぎず、実際に的を射ていません。
仙台高裁棄却決定 P12
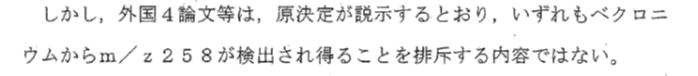
⇒ 当たり前です。ベクロニウムの質量分析に関する論文で、なぜわざわざ特定の質量のイオンが検出され「ない」ことを言わなければならないのでしょうか?全くナンセンスな指摘です。
仙台高裁棄却決定 P12
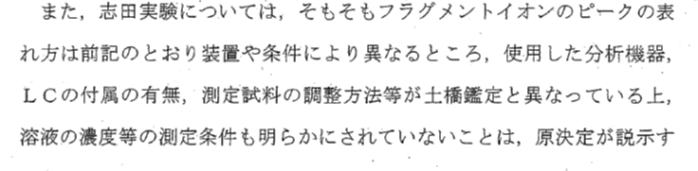
⇒ 志田実験は土橋鑑定の再現実験ではありません。あくまでベクロニウムから開裂でm/z258が生じるかどうかを確認する実験です。実験の目的が違うのですから、測定条件が異なるのは当然です。また、測定条件が気になるのであれば、なぜそれを4年間もあった即時抗告審の審理期間中に弁護側に確認しなかったのでしょうか?また、何故、弁護側が求める鑑定人の証人尋問請求に応じなかったのでしょうか?
仙台高裁棄却決定 P13
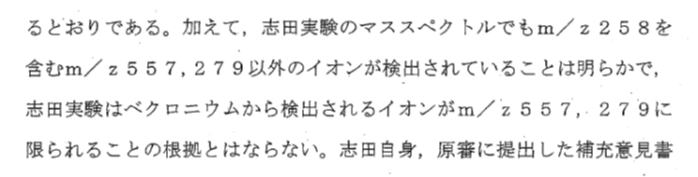
⇒ 既述したように、志田実験は、通常のESI法ではなく、意図的に(コーン電圧を高圧にする)過酷な条件を作り出して分析対象化合物の開裂を引き起こす手法で、志田実験で検出されるイオンの種類と、通常のESIで検出されるイオンの種類は全く異なります。通常のESIでは開裂は全くあるいはほとんど起こりませんので、そもそも検出しているものが違います。(前者はベクロニウムのフラグメントイオン、後者はベクロニウムの分子量関連イオン)高裁決定の上記部分は、志田実験の意義を全く理解していないか、意図的に無視(ないしは歪曲)したものです。また、志田実験でm/z258を検出しているとされていることについては次の通りです。
仙台高裁棄却決定 P13
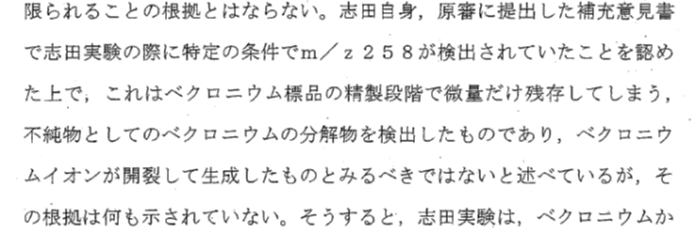
⇒ 志田実験では、m/z258付近にごく微細なピークが認められますが、その他のm/zでは微細とは言えない多くのはっきりしたピーク(ベクロニウムイオンが開裂して生成されたイオン)が検出されています。もしm/z258付近のごく微細なピークがベクロニウムイオンが開裂して生成したものであるならば、なぜその他のイオンのように大きなピークにならないのでしょうか?これは補充意見書が述べるように、精製段階で微量だけ残存してしまう不純物(ベクロニウムの分解物)、あるいは装置にかける前に試料調整段階でできた微量な加水分解物と見るのが妥当でしょう。この部分は検察意見書が指摘したものですが、ほとんど難癖に等しいものです。
仙台高裁棄却決定 P13
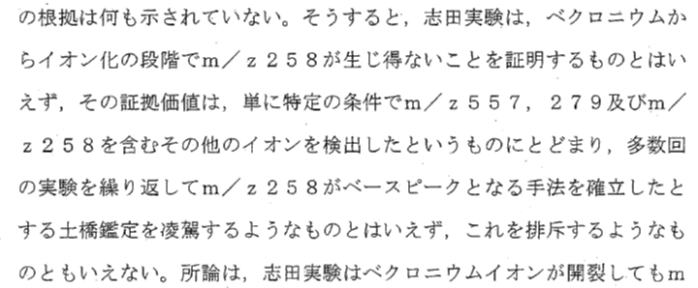
⇒ ベクロニウムから質量分析(LC/MS)でm/z258がベースピーク(スペクトル中でもっとも強度の強いピーク)として検出されるとする主張は世界中で土橋以外に誰も言っていません。土橋が過去に学会で発表(1999法中毒)したとするものも、学会誌にごく簡単な要旨しか載っておらず、実験データも添付されていません。こんなものをもって手法が確立されているなどとは到底言えません。手法が確立しているどころか誤った手法または(および)認識であると考えられます。土橋自身も誤りに気付いたためか、2002年以降の著述では、それまでの主張(m/z258がベースピークとして検出される)を完全に引っ込め、ベクロニウムの質量分析における指標となるイオンとして、m/z279や557を挙げています。(弁護側補充意見書より)
仙台高裁棄却決定 P14
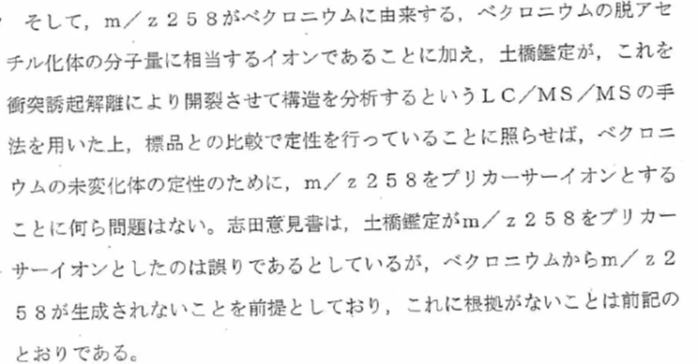
⇒ m/z258をプリカーサーイオンとするのが誤りであるのは、m/z258が土橋が検出したと主張するベクロニウム(の未変化体)に特徴的に検出されるイオン(ベクロニウムの未変化体の質量を反映するイオン=分子量関連イオン)ではないからです。ベクロニウムの脱アセチル化体であれば、m/z258はその質量を反映するイオンですので、これをプリカーサーイオンとするのは正しい方法ですが、未変化体の定性(同定)にこのイオンを用いることは誤りです。比較鑑定だから問題ないと言うのでれば、少なくとも再鑑定を行って検証できるように、資料を残しておかなければなりません。本件のように再鑑定できない状況で、一般に認められていない独自の鑑定方法を証拠として用いることは許されません。
仙台高裁棄却決定 P14
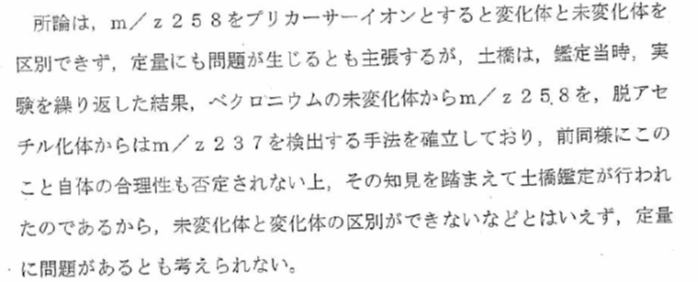
⇒ 既述しましたが、土橋が事件以前に学会で発表した、質量分析(LC/MS)でベクロニウム未変化体からm/z258を、脱アセチル化体からm/z237を検出したという知見はおそらく実験手法または(および)認識に誤りがあり、正しくは未変化体からm/z279を、脱アセチル化体からm/z258を検出しなければなりません。土橋のような主張は土橋の他に世界の誰もしておらず、そのような知見を客観的な化学分析に用いることはできません。従ってベクロニウム未変化体からm/z258を検出するような土橋の方法では、変化体と未変化体の区別ができず、裁判所や検察が言うように分析過程で変化したとすれば、分析の度に変化体と未変化体の比率が変わることになりますので、検量線が直線にならず、定量はできません。なお、定量ができなければ、ベクロニウムの資料中の含有量がわからないわけですから、(鑑定資料が残されておらず、再鑑定もできない、いくらでも偽造可能な内容の鑑定書しか残っていない鑑定であることを踏まえれば)有罪の立証はできません。(なお、検察側は検量線は当然作成したとしていますが証拠として出されていません。)
仙台高裁棄却決定 P15
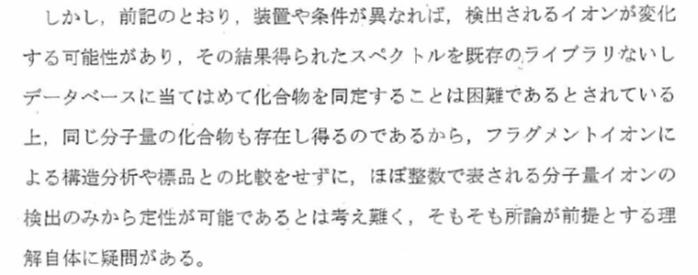
⇒ 「装置や条件が異なれば・・・」については既述の通りです。後半で裁判所は、あたかも志田意見書が分子量関連イオンの検出のみで定性が可能であると主張しているかのような書き方をしていますが、志田意見書は全くそんなことを言っていません。志田意見書が言っているのは、ベクロニウムの定性(同定)のためにはまず最低限、分子量関連イオン(当該化合物の質量を反映するイオン)を検出しなければならない、ということです。理解が間違っているのは志田意見書ではなく裁判所の方です。(なお、「理解自体に疑問がある」などの表現は土橋意見書や検察意見書の受け売りです。)
仙台高裁棄却決定 P15
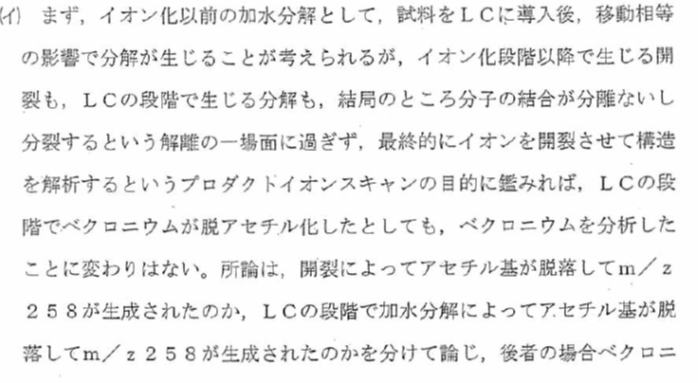
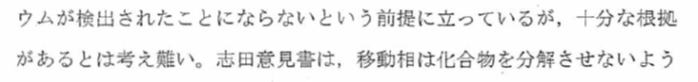
⇒ LCの段階で加水分解するような場合、「ベクロニウムが検出されたことにならない」というよりも、意図せずして分析過程で加水分解させてしまうような鑑定には信頼性がなく、証明力がないということです。実際に意図せずして分析過程で加水分解させてしまうような鑑定では、既述のように変化体と未変化体の比率がわからなくなりますから定量はできなくなりますし、標準品との比較鑑定において、標準品(未変化体)から変化体を検出したことになり、比較鑑定の前提が崩れてしまいます。そのような鑑定には科学的信頼性はなく、従って証明力がないということです。
仙台高裁棄却決定 P16
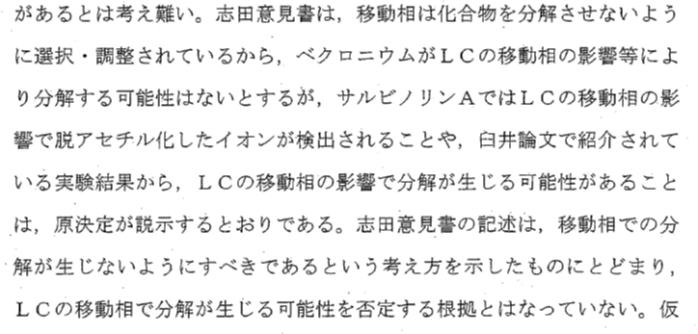
⇒ 臼井論文(検察が原審(=地裁)に提出した証拠資料)の実験結果で示されているのは、試料の「保存溶液」が試料の分解を引き起こすことがあるということ、また、LCの移動相の流速が「分析時間」や「分離度」に影響を与えること、LCのカラムのサイズ(長さ)が分離能に影響を与えることなどで、LCの移動相の影響で分解が生じるなどという直接の記載はありません。仙台地裁の原決定および仙台高裁の決定は、科学論文をろくに読解も理解もせずに勝手な間違った引用をして、結論ありきの結論に結び付けているだけです。また、意図せずして分析過程で加水分解させてしまうような鑑定には信頼性がなく、証明力がないことは既述の通りです。
仙台高裁棄却決定 P16
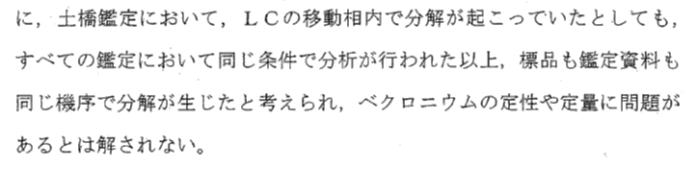
⇒ 既述しましたが、意図せずして分析過程で分解してしまうような鑑定では、変化体と未変化体の比率がわからなくなりますから、(検量線が直線にならないので)定量はできなくなります。また、標準品との比較鑑定において、標準品(未変化体)から変化体を検出したことになり、比較鑑定の前提が崩れ、そのような定性には科学的信頼性はなく、従って証明力がないということになります。上記の裁判所の判断は(毎度のことながら)鑑定や分析の科学的背景を全く理解していない勝手な素人判断です。
仙台高裁棄却決定 P16〜17
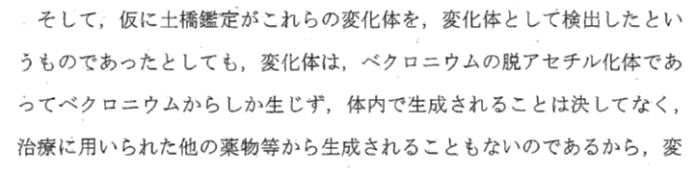
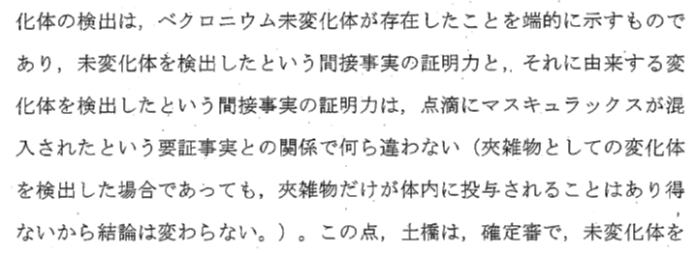
⇒ 考え方の論理が逆転しています。土橋自身は未変化体を検出したと今でも言っており、変化体を変化体として検出したわけではありません。そして、既述のように土橋の鑑定手法では定量ができず、定性の信頼性もありませんので、ベクロニウムの未変化体検出の証明力も、変化体検出の証明力もありません。元々本件は、鑑定資料を全量消費したなどとして、再鑑定ができない状況下で、資料(血液、尿、点滴液)が誰のものかも、さらに資料が本当に血液や尿であることの証明もできないような、いくらでも捏造可能な「鑑定書」しか残されていないわけですから、元々極めて限定的な証拠価値しかないものです。その「鑑定書」の中身が、変化体と未変化体の区別もつかないようないい加減なもので、他のどの論文にも出てこない数値を根拠とするような客観性のないものであれば、マスキュラックス混入よりも、まず「鑑定書」の証拠価値を疑うべきでしょう。裁判所の判断は、まず事件ありき、結論ありきのもので、科学の原則にも刑事裁判の原則にも真っ向から反するものです。ましてや標準品の中にごく微量しか存在しない「夾雑物」の検出に正当性を認めてしまうような判断は狂ってるとしか言いようがありません。
仙台高裁棄却決定 P20
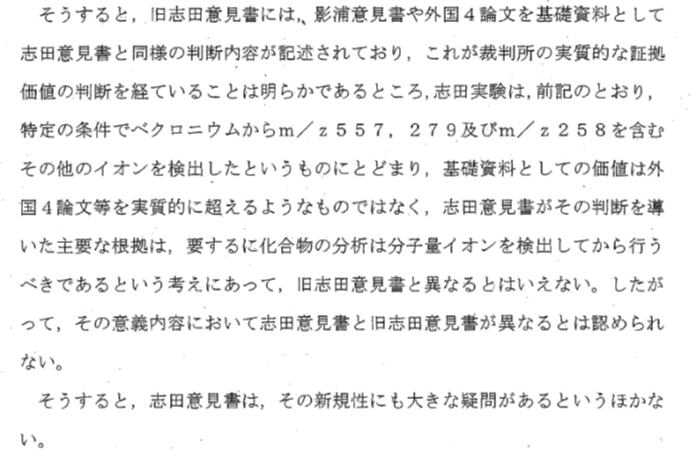
⇒ 再審で提出した志田意見書は、検察の確定上告審段階での主張(=m/z258はベクロニウムから開裂によって生じた)へ反論するために、特別の条件下で開裂が起きやすい状況を作り、どのようなイオンが検出されるかを確認した志田実験をもとにしたものであり、そのような実験に基づかない確定審段階での旧意見書とは証拠価値が異なります。よって明らかに新規性があります。
仙台高裁棄却決定 P26
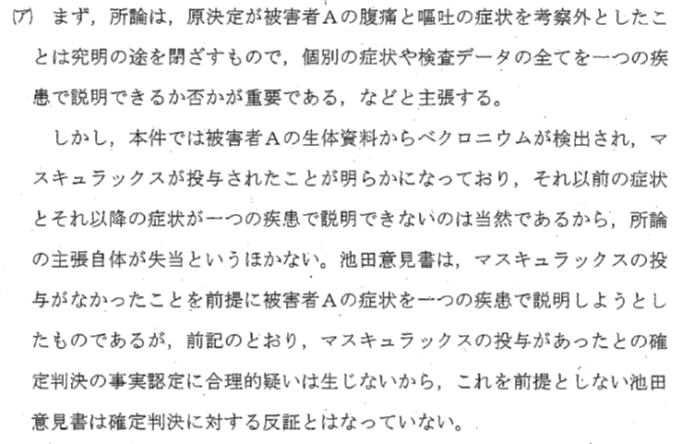
⇒ 「本件では被害者Aの生体資料からベクロニウムが検出され、マスキュラックスが投与されたことが明らかになっており」とのことですが、まさに現在、再審において争いになっている論点について、弁護側が認めていない事実について、自らの勝手な判断で「明らかになっており」とはどういう了見でしょうか?「主張自体が失当というほかない」のは裁判所の方でしょう。「これを前提としない池田意見書」とのことですが、争いになっている論点について、何故片一方の主張を「前提」としなければならないのでしょうか?理不尽にも程があります。
仙台高裁棄却決定 P26
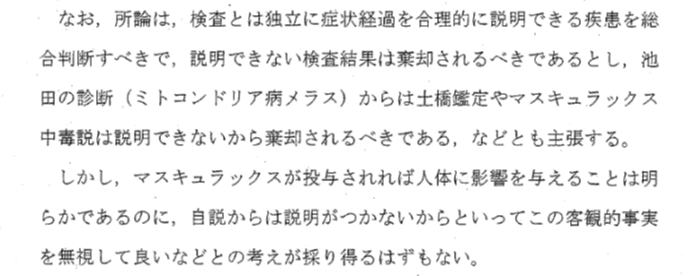
⇒ 「この客観的事実」とは一体何を指しているのでしょうか?「マスキュラックスが投与され」たことを指すのであれば、前述と同じで、これは客観的事実などではありません。「マスキュラックスが投与されれば人体に影響を与えること」であるならば、それは当然のことですが、客観的事実ではないことを前提にしているので、意味がありません。
全量消費したとして再鑑定もできない、いくらでも捏造し得る「鑑定書」が信頼できて、神経内科専門医の診断が信頼できないとする根拠は何なのでしょうか?
仙台高裁棄却決定 P27
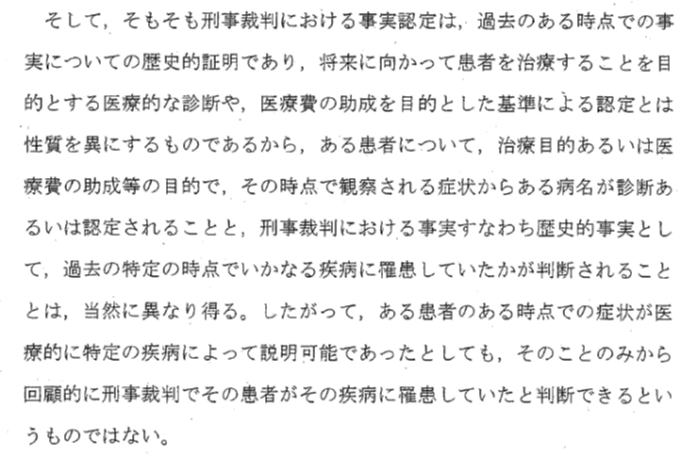
⇒ この部分は要するに、前述、前々述で取り上げた部分と同じで、マスキュラックスが投与されたことを前提として、刑事事件ではそのようなことも起こり得るのだから、必ずしも医学的診断が当たるとは限らない、ということを、回りくどい、もっともらしい言葉を使って説明したものと思われますが、全くナンセンスな話です。マスキュラックスが投与されたことが客観的事実でないのは前述の通りですが、「そのこと(医学的診断)のみから刑事裁判で患者がその疾病に罹患していたと判断できるというものではない。」などと言うのであれば、全量消費したとして、再鑑定もできない、いくらでも捏造可能な「鑑定書」のみからマスキュラックスが投与されたと判断できるというものでもない、ということも言えるでしょう。
医学的診断が(刑事)裁判において役に立たないというのであれば、医療を背景にした事件や裁判において、医者の証言や意見書は不要ということになってしまいます。上記記述はあくまで本件がマスキュラックス投与による事件という前提に立ち、それに反する全ての証拠に目を塞いでいるだけの話です。
仙台高裁棄却決定 P27〜28
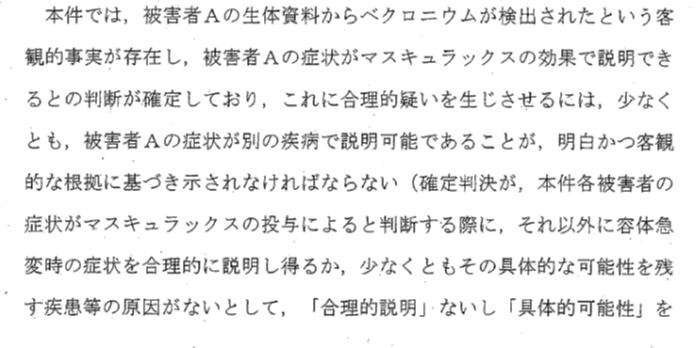
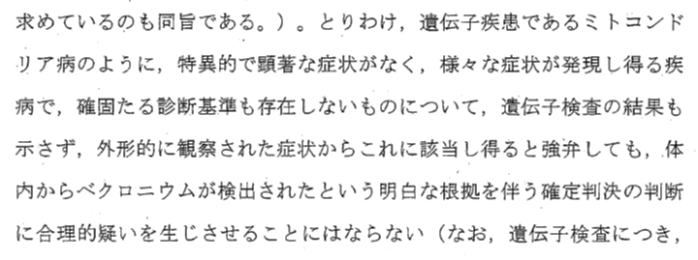
⇒ A子さんの急変前後の症状は、ミトコンドリア病の国の認定基準に合致しており、確定判決が求めている、「それ以外に容体急変時の症状を合理的に説明し得る」、「少なくともその具体的な可能性を残す疾患等の原因」にまさに当てはまっています。「合理的疑い」というのは、刑事裁判の原則である、「疑わしきは被告人の利益に」(再審にも適用される)を踏まえたものであって、高裁決定が求めているものはこの原則と真逆の「無実の証明」です。高裁の判断は刑事裁判の原則を履き違えたもので、不当です。
仙台高裁棄却決定 P29
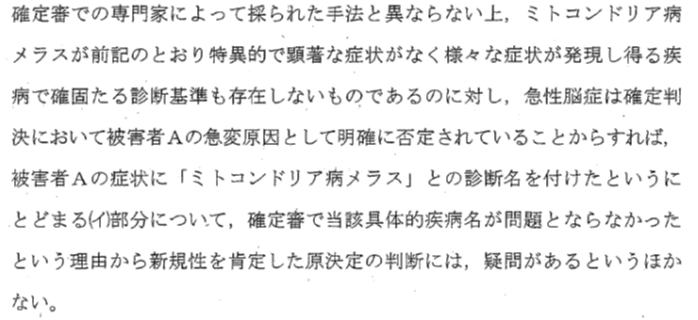
⇒ 確定判決において、急性脳症は明確に否定されていません。(地裁判決でA子さんの急性脳症の可能性に触れた部分は僅か1ページ半ほど。高裁判決では全く触れられていません。)そもそも確定審、特に一、二審では、弁護側の主張として、患者の急変症状が筋弛緩剤によるものではないという点に主眼が置かれ、急性脳症は真の急変原因の一つの可能性として出されていたに過ぎず、積極的に主張されていたわけではありませんでした。よって池田意見書の意義は、被害者A(A子さん)の症状に具体的な診断名を付けることによって、真の急変原因(病因)を特定したものであり、十分に新規性があるものと言えます。
|
|