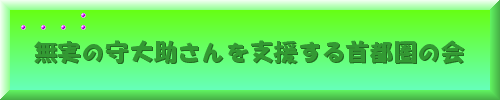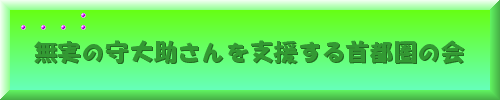|
| 〜警察・メディアの合作冤罪ー仙台・北陵クリニック事件〜 |
※本文章は2007年12月1日、「守大助さんを支援する東京大集会」における山口正紀氏の講演を事務局が聞き取り、要旨を掲載したものです。文章の責任は全て事務局にあります。
2003年末に退社するまで、読売新聞で30年間、記者の仕事をしてきた。記者生活の半分以上の期間、取材・報道に携わる一方で、「人権と報道・連絡会」世話人として、報道被害者の支援にかかわるとともに、新聞がいかに人権侵害をしているか、間違った報道をしているかを社会に知らせるという、「会社の仕事」とぶつかるような活動をしてきた。
この「北陵クリニック事件」については、古くからお付き合いのある阿部泰雄弁護士に事件の話を聞き、おかしいとは思っていた。しかし、裁判資料を読んだり判決公判を傍聴したりして、これほど酷い冤罪事件はあるかと、とりわけ二審・仙台高裁の訴訟指揮の酷さにあきれかえった。しかも、その裁判の実態をチェックしないメディアの在り方という点で、今の日本の酷い裁判状況、メディア状況を象徴する事件だと思っている。今日はこうした視点から、特にメディアの問題を中心にお話したい。
●事件ではない「作られた事件」
最初に事件の大きな流れをお話したい。この事件は、まさに「つくられた事件」だ。普通の事件では、被害者がいて犯人がいる。ところが、この事件ではまず、被害者がいたのかどうか、果たして事件だったのかどうか、そのものを疑わなければいけない。
類似した事件に1974年に兵庫県西宮市で起きた「甲山事件」がある。甲山事件では25年の闘いを経て最終的に無罪判決が確定したが、知的障害児の施設で園児2人が浄化槽に落ちて死亡したのを、警察は最初から殺人事件と思い込み、メディアもそれを殺人事件として報道する中で冤罪が作られた。長い裁判を通して、実は不幸な事故であったということがわかってきたのだが、北陵クリニック事件も、この甲山事件と似ている。
2001年1月6日、入院中の小学校6年の女の子に筋弛緩剤を点滴したとして、宮城県警が守さんを殺人未遂容疑で逮捕し、それと同時にメディアが一斉に全国的な大事件として報道した。守さんは6日から8日までの間に警察で自白強要の取り調べを受け、捜査員の強要、脅し、あるいは熱で頭がふらふらする中で、無理やり断片的な自白調書をとられ、それが大々的に報道された。
しかし、9日に弁護団が面会し、どういうふうにやったのか聞くと、守さんはやっていないから答えられない、というところから守さんの無実の訴えが弁護団に伝わった。警察はその後も、逮捕・再逮捕を繰り返し、実に計5回も逮捕して、その間ずっと密室で自白を迫る拷問に近い捜査・取り調べを行った。
裁判は、一審初公判で守さんが全面的に無実を主張して始まった。弁護団は「これは、事件はでない」ということを具体的なポイントを示して説明した。一番大きな問題点は、そもそも筋弛緩剤で人を殺せるのか、しかも点滴に筋弛緩剤を入れて人を殺せるものなのか、という問題。これについて弁護団は、初公判から問題点を具体的かつ明快に指摘した。さらに「被害者の尿や血液、点滴ボトルから筋弛緩剤が検出された」とする鑑定そのものが、でたらめなのではないかという点や、急変患者続出の背景にあった、病院が抱えていた経営難などの問題点を指摘した。
これら初公判で弁護団が明らかにしたいくつかの論点を併せ考えると、この時点で検察は公訴を取り下げるべき事件だったと思う。しかし、一審判決は大阪府警科捜研の鑑定をほぼ唯一の証拠として有罪・無期懲役判決を言い渡した。
二審では、弁護団は福岡大学・影浦教授の「科捜研の鑑定で出たとされるものは守さんが点滴に混入したと言われるマスキュラックスの主成分ベクロニウムではない」という鑑定意見書を提出した。事件そのものがひっくり返る重大な指摘だった。その後、弁護団は何人かの証人、証拠を申請するが、その後が前代未聞の裁判進行になっていく。
実質審理がほとんどない状態で、わずか3回目に事実調べ打ち切りたいと裁判長が言い出す。被告人も弁護団も傍聴人も誰もいない場所で、裁判長は判決期日を指定したことにした。期日指定は公の場で行わなければいけないという決まりを無視した暴挙だ。それに抗議した弁護団のあらゆる申し立てを裁判所はすべて却下した。
私は二審判決公判を傍聴した。かつての公安事件、いわゆる過激派裁判ではよくあったことだが、刑事裁判でこれほど次々と退廷の声が出る法廷を見たのは久しぶりだった。始めから裁判長が考えていたかのように、廷吏が傍聴者の後ろに来てチェックし、裁判長が指をさすとすぐに立たせるという乱暴なやり方だった。弁護団も7人のうち4人を退廷させ、ついには守さん本人も退廷させる。判決朗読最後の段階になるともうほとんど法廷に誰もいない。私は抗議したいのを一生懸命我慢して最後までメモをとった。
二審判決は、実質審理をしてないから判決内容は一審を写しただけの中身の無いものだったのは当然だ。守さんは上告し、現在に至っている。
●冤罪に加担したメディアの犯人視報道
メディアの話に移ると、私は1973年に新聞記者になって30年間仕事をしてきたが、当初から事件報道の在り方に大きな疑問を持っていた。とにかく警察情報をとってこい、と言われる。警察にもらった情報をどれだけ早く書くのかが記者の仕事になっている。警察情報は、どんな裏付けがあってどこまで正しいのかなど、記者自身がチェックする作業なしにそのまま書いている。そういうことに疑問を持ち、悩みながら仕事をしてきた。
今回の事件を見ても、記者たちがそういう警察の発表やリークを疑った形跡がほとんどない。それどころか、警察が公式に発表できない断片的な情報まで、あたかも確定した事実のように大々的に報道する報道合戦が繰り広げられた。
逮捕翌日の2,001年1月7日の新聞は、新聞の事件報道を疑う習慣のある私でさえ、「これは凄い事件が起きた」と思ってしまうような紙面だった。全国紙全部が一面トップ、社会面トップの最大級事件の扱い。例えば朝日新聞一面トップは「容体急変十数人/7,8人死亡」というショッキングな見出し。社会面では「命救う病院でなぜ」と、最初から筋弛緩剤点滴による事件と断定した上での犯人視報道になっていた。
94年6月、松本サリン事件が起きた時、警察が家宅捜索した段階で全国の新聞、テレビ全てが「河野さんが自宅の庭で農薬の実験をしていて毒ガスが発生した」と報道した。「住宅街の庭でなぜ」という見出しが躍り、誰もが河野さんを犯人と思った。この事件も、そのやり方と全く同じ。「不審な死、数人」のように容疑は殺人未遂でありながら、既にたくさんの死者が出ていることを印象付ける大々的な報道が行なわれた。
さらに、大きなポイントは被害者の数を競う報道。被害者が多ければ多いほど事件が派手になっていく。実際に記者が調べていない話でも、断片的な警察情報を被疑者にくっつけていくという報道パターンの典型。8日の読売が一面で「10人近く死亡」、社会面で「恐怖の点滴」と報じ、その後は各紙の数争い。9日の毎日は「20人点滴、約10人死亡」。およそこの数日間で、全国の市民は「10人殺した」というイメージを植え付けられた。
さらに「犯人」と印象付けたのが自白報道。守さんの供述内容は自白とも言えないようなレベルだが、メディアは全面的な自白をしたかのように報道した。8日の一面朝日の見出しは「『待遇に不満』と供述」。朝日は2週間連続でこの事件を一面で扱うという、朝日の事件報道史上空前の大報道をやった。続いて8日の毎日は「『他の患者も』ほのめかす」。10の日読売「『十数人に薬物』と供述」。読者は、本人が自白しているとなると犯人に間違いないと思ってしまう、私たちが報道にひっかかりやすい部分だ。ときにはやっていなくても「自白した」という情報を流し、犯人と印象付ける手法を警察は意図的にとる。
守さんは9日の段階で自白を翻し、否認に転じているにも関わらず、メディアは10日以降も延々と自白報道を続けた。10日の読売「いろんな不満」。10日の毎日「副院長ら困らせたかった」。こんなものが動機になるのかとしか思えない。11日の朝日「仮面だった?好青年」「患者にいじめ」「すぐキレる」。自白報道だけでなく、悪人視報道も加わった。13日朝日「医師の腕試す」「地位にも不満」。13日毎日「安い給料」「ゆがんだ自尊心」。
10日以降、2週間近く続いた報道は、本人が否認しているにも関わらず「自白を続けている」と書いており、すべて誤報だ。弁護団から何も取材せず、警察情報だけで記事を書いているかの証拠。1月18日のNHK「クローズアップ現代」に対し、弁護団が放送中止を申し入れた後、書くメディアはようやく「否認」と報道した。だが、この後も警察の再逮捕のたびに大々的な犯人視報道が繰り返された。
●冤罪裁判・判決の問題点を伝えないメディア
メディアの問題は、捜査段階、起訴段階で警察情報を鵜呑みにして垂れ流すだけではない。次の大きな問題は裁判報道だ。初公判で弁護側の主張に妥当性があると考えられれば、捜査段階の報道は軌道修正しなければならない。弁護側の指摘を受けて科学的な観点で調べ直さなければいけない。しかし、実際には裁判が始まると、「検察・弁護側双方の意見」として、事実上弁護側の主張を検察側の主張で消していくような報道が行なわれた。
メディアは、有罪判決ならそのままだが、無罪判決が出ると一転して自白偏重捜査を批判したりする。メディアは常に無罪、というのが報道の常套手段だ。
この事件の一審判決報道では、守さんを犯人と思いこんだ被害者のお母さんの話を全面的に取り上げ、大きな見出しで情緒的に同情を誘うような形で報道した。朝日「有罪・・・戻らぬ意識」「15歳少女 無言の青春」「傍聴の母親、涙ぬぐう」。読売「3年半・・意識戻らぬ娘」「「有罪」母の目に涙」「高校入学の春のはずが」。毎日「あの子に謝って」「涙で聞く被害者母」。無実を訴えている人に対して、いくら有罪判決が出たからと言って「謝って」などと、犯人を大前提にした報道をする。これは報道ではない。
被害者・遺族は、往々にして警察に言われた情報を信じて話す傾向があるが、それはメディアの側から見れば1つの情報に過ぎない。しかし、それを情緒的に流すことにより、読者・視聴者は被害者の訴えに簡単に感情移入してしまう。
一審判決でメディアが問題にしなければならなかったのは、判決が鑑定資料全量消費を「問題がない」としたことだ。鑑定資料を残しておかなければいけないことは、警察の捜査規範にも書いてある。この事件では、警察の鑑定は「5件すべてについて資料を全部使ってしまった、頼まれてもいないことまで調べた」ということになっている。これでは再鑑定のしようがない。証拠として出てきたのは大阪府警科捜研の現物のないただの文書、字面にすぎない。そんなものを最大の証拠として無期懲役という重罰を下していいのかということをメディアの記者は疑問に思わなければいけない。
しかし、少しでもこの判決に疑問を呈したのは、判決日夜のNHK「あすを読む」で解説員が述べた「資料が残っていない場合は証拠として認めないことが必要ではないか」という指摘だけ。深夜番組だけでなく7時のニュースでも9時のニュースでも言うべきではないか。新聞は、この疑問を完全に無視した。警察や裁判所の言うことに対して疑問を提示し、読者が多角的に考えられるよう問題提起する機能が、日本のメディアにはなくなっているということをはっきり示した。
また、二審の判決報道で田中裁判長の酷い訴訟指揮を批判したのは、東京新聞の解説記事のみ。「実質的な審理はほとんどなく四回の公判で結審。・・一審判決に対する弁護側の疑問を積極的に解明しようとしたとは言い難い訴訟指揮だった」と当然のことを書いた。ところが、産経新聞は「今回の訴訟指揮は、時代が求める『適正な刑事裁判』への一つの答えになるだろう」と評価した。こんな判決や訴訟指揮が「時代が求める裁判への答え」になるのだったら、もう裁判はやめましたと言った方がいい。
●犯人断定報道に影響される裁判官たち
次に、この事件に限らず事件報道での特徴について話したい。1つは警察情報を鵜呑みにした逮捕・自白報道。警察発表を全く疑わず大々的に報道し、動機についても誰でも感じる疑問をとりあげず、否認した後でも自白報道を続ける。被害者の数を競い、より派手にセンセーショナルに報道した方が得で評価されるというメディアの状況がある。自分も若い頃に経験があるが、自分の取材で確認できた事実だけで書いていこうとすると他社に比べて地味になっていく。すると、デスクから怒られてしまうという状況がある。
もう1つ重大な問題は、この事件でも大きなポイントだと思うが、これだけ大々的な犯人視報道が行われると、裁判にも直接大きな影響を及ぼす。建前では裁判官は起訴状一本主義といって起訴状を見るまで白紙でいなければならないことになっているが、これだけシャワーのように大騒ぎしていれば影響されずにいられない。
それどころか、知り合いの何人かの元裁判官に聞いたことだが、裁判官たちは事件が自分のところに回ってくるかもしれないと、皆自分の地域で起きた事件報道を必死で読んでいる。その時点で、頭の中に犯人イメージができあがっていく。その犯人イメージを覆して無罪判決を出すには大変な勇気がいる、というふうな意識がつくられていく。
この事件では、「捏造をうかがわせる事情はない」として鑑定資料の全量消費を問題にしなかった一審判決や、最初から審理の必要がないというような二審の裁判指揮にそれが表れている。犯人視報道は、これだけの重大な影響を裁判官に与えた。
かつて、いくつか無罪判決を出した裁判官が、週刊誌に「無罪病」のように書かれた。このようなメディア状況の中では、裁判官は有罪判決を書く方が楽だと考える。こういう報道・裁判の構造の中で、このような問答無用の判決が出てきたと思っている。
ロス疑惑の二審逆転無罪判決では、報道が一審の有罪判決に大きな影響を与えたと、二審判決が述べている。いかに裁判官が報道に影響されるかを物語る。
袴田事件の一審で有罪判決を書いた元裁判官の熊本さんが今年2月、「判決を書いたとき、実は無罪の印象を持っていた」と告白して話題になった。熊本さん以外の2人の裁判官は当時の大報道の影響で有罪心証を持っていたが、熊本さんは事件後に静岡に赴任してきて報道の影響を受けていなかったことが、背景にあった。
今年初めに無罪判決が出た鹿児島の志布志事件や無実が明らかになった富山の強姦冤罪事件でも、事件当時は、自白報道と犯人視報道が行われている。メディアは無罪判決が出たときだけ捜査や裁判のあり方を批判するが、法廷で無実の証拠がたくさん出ているにも関わらず有罪になった事件、被告人が無実を訴えている事件こそ、もっともっと意識的にとりあげて報道しなければいけないと思う。
つい数日前にも広島の放火殺人、死刑求刑事件で無罪判決が出た。朝日新聞が社説で「自白だけに頼る危うさ」という見出しの社説を書いていたが、なぜ自分たちの報道には目が向かないのか。新聞は、常に自分たちは正しいという傲慢な姿勢だ。このようなメディアの在り方が多くの冤罪事件を生み出し、世論の犯人視や裁判官にプレッシャーを与えている。この構造を変えていくためにも、最高裁で森さんの逆転無罪を勝ち取り、その中でメディアの在り方、危険性について知らせていく闘いを皆さんと一緒にやっていきたい。
「冤罪加担・人権侵害報道の構造」として、話したいことはたくさんあるが、時間がないのでレジュメを読んで考えていただきたい。
最高裁になると調査官の判断一つというところがあるが、その判断の中には世論の声が届けば無視できなくなるという要素もある。例えば提案だが、最近の一連の無罪事件とこの事件を結び付けて自白強要の問題や裁判の形骸化の問題等を新聞にどんどん投書する。そうして、たくさんの人、世論に知らせ、裁判官や調査官の目にとまるような活動をやっていけば、最高裁の裁判官も無碍に上告棄却できなくなる可能性があると思う。
全国のたくさんの冤罪事件で、やってもいない罪で6年も7年も、あるいは20年も30年も閉じ込められている人たちがいる。その事実を知れば「そんなことは許せない」と思う人は多いと思う。そういう人々に訴えかけていく活動を皆さんと一緒に進めていきたい。
|
|
|
|